旗竿地の家


この記事は、広報誌「榊住建だより」との連携記事です。
榊住建だよりは、年2回(夏・冬)に発行しています。
よろしければ、文末のサムネイルをクリックして参照ください。
編集する
住宅街の奥まった旗竿地。
曲がり路地と細いアプローチを味方に、大胆な発想で生まれた川田さんのご自宅があります。

川田さんは大学卒業後に編集プロダクションに就職。
東京23区を一つずつ巡って実際に住みながら、その区を毎号特集する雑誌づくりに取り組み、そのユニークな手法が業界内外や海外で注目されました。

独立後に携わったカルチャー誌で、アジア特集号を3号連続で制作したことをきっかけに目覚めた、アジアの魅力。
その後、興味関心の赴くままに個人的な文化調査・研究プロジェクトとして頻繁にアジア各地を訪れ、まとめた冊子を出版しました。
新型コロナウイルス感染症が流行し始めたのは、次の企画を考えていた矢先のこと。
海外渡航が困難になったことに加え、第二子となる長男が誕生したことが、戸建て住宅の建設を決意するきっかけとなりました。
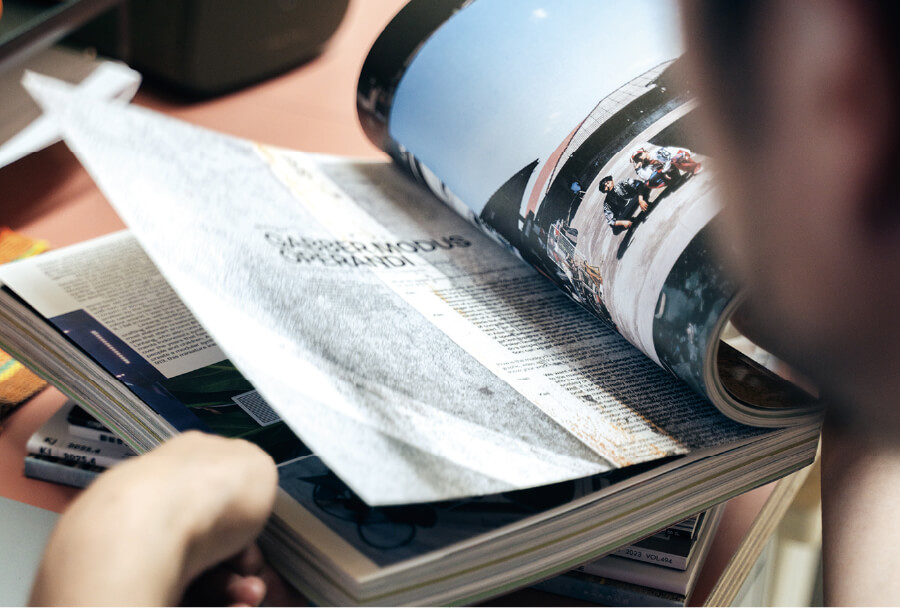
家づくり
川田さんが大切にしたのは、関わる全員が能力を存分に発揮し、面白いと思える家づくり。
家族構成など最低限の情報だけ共有し、仕事ぶりに惚れ込んだ建築家ICADAの岩元真明さんへは
「意義あるプロジェクトにしてほしい」
と告げ、設計は丸ごと託しました。

熊本県小国町の森で育ったスギの“大径木”が、住まいの柱と梁に骨太の表情を与えています。
しかし、その厚みは同時に割れやねじれのリスクも孕む繊細さの証。
そこで力を貸りたのが小国町で穴井木材工場を営む製材家の穴井俊輔さん。
温泉地ならではの“地熱”を利用した独自の低温乾燥で、木のポテンシャルを最大限に引き出しました。

写真は、岩元さんが教壇に立つ九州大学の岩元研究室の学生さんも交え、柱や梁に使う木材を選定。(熊本県小国町)
立地は路地が屈曲する旗竿地で、構造設計を担当したのは、新しい設計の可能性を追究している建築士の荒木美香さん。
一般的な木造民家では家の中央に柱を入れるのが一般的ですが、大径木、一本一本を柱として生かす特殊な構造設計にしたことで、木の力強さと大らかな空間が家全体に息づいています。

特殊な立地、構造設計がゆえに施工先探しは難航する中、引き受けたのが榊住建でした。
「話を聞いた時に、まず面白そうだなと思いました」と担当の大野。
時には真剣に、時にはワクワクと——。
何度も話し合いを重ねながら、木の温もりが暮らしに寄り添う住まいが完成しました。
大径木に包まれた家



大径木の加工や構造設計など、多彩なプロフェッショナルが力を合わせて形にした川田邸。
その中心に立っていたのは、何事も面白がってしまう遊び心いっぱいの川田さんです。
「家づくりというワクワクする体験は、誰もが一度味わうべき」
と語る横顔から、充実した暮らしぶりが伝わってきます。
- 設計:ICADA 岩元真明
- 構造設計:荒木美香構造設計事務所
- 材木製材:穴井木材工場
- プレカット加工:肥後木材株式会社
- 大工:株式会社田代工務店
- 施工:榊住建

